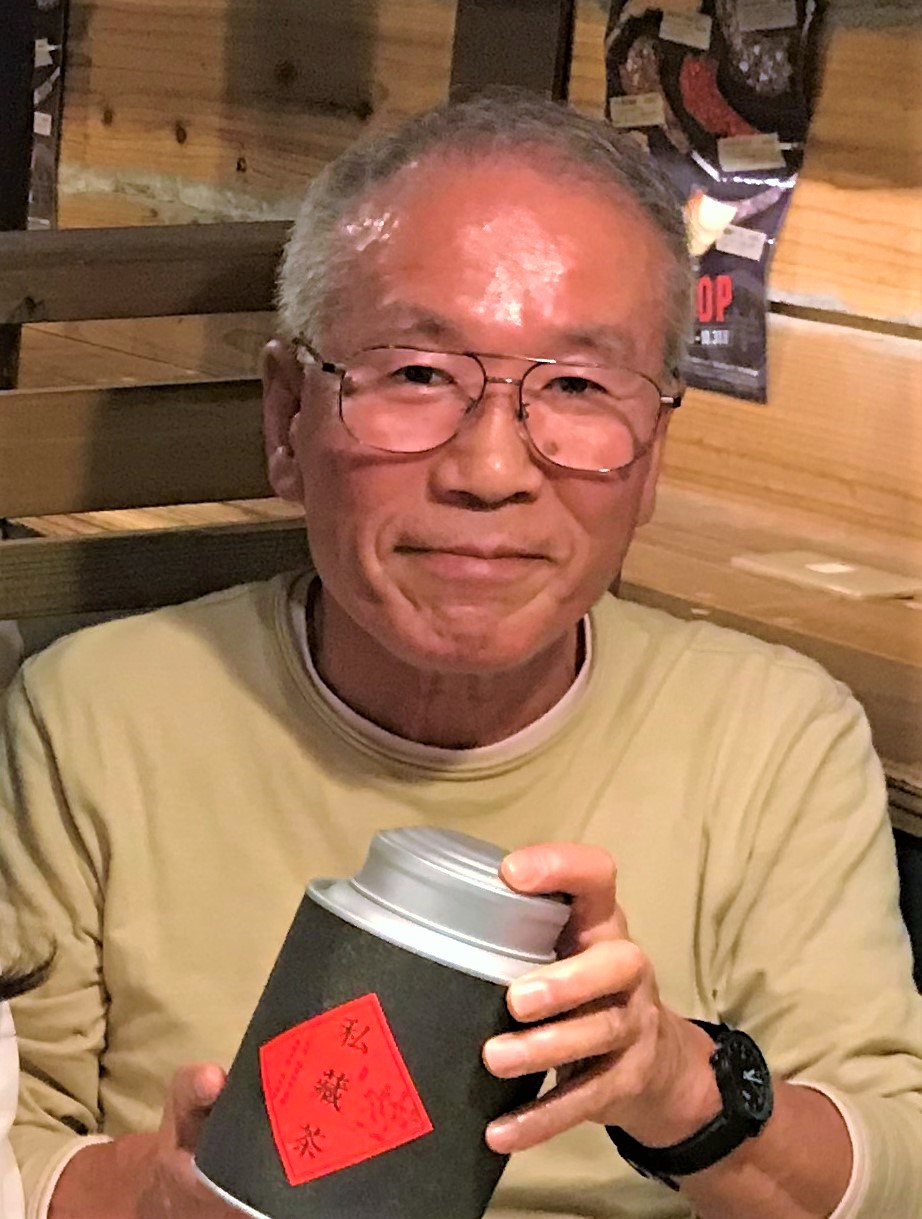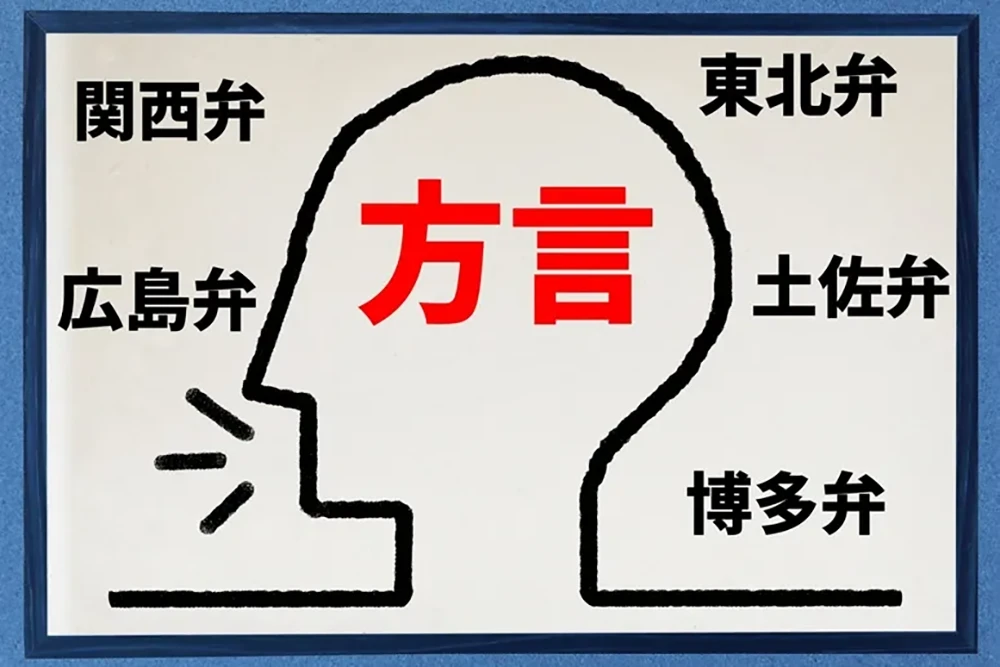「四字熟語」はおもしろい
「パリ五輪開会式 セーヌ川での入場は複数国での『呉越同舟』も」
これは、パリ・オリンピック開会式の様子を伝えた記事で、毎日新聞ほか、多くの媒体で報道されたものです。
この中のたった4つの漢字の言葉、「呉越同舟」の意味を知っているか知っていないかで、この記事の面白さがまるで違います。いったいどういう意味なんでしょうか?
呉越同舟(ごえつ・どうしゅう)とは?
この新聞の記事では、続いて「国・地域により、競技ではライバル関係にある複数国が一つの船に乗り込んで紹介される『呉越同舟』となった」と紹介されています。これでだいたいの意味は分かるでしょうが、実はこの言葉は、昔から伝わる興味深い逸話や教訓などを含んだ故事成語なのです。
中国、春秋時代の呉国と越国は、宿敵同士で大変有名でした。しかし両国の人が同じ舟に乗り合わせ、突然大風が吹いてきたら、たとえ敵同士でも、舟が転覆しないようお互いに協力するだろう、というのです。この話は兵法書の『孫子』にあるものですが、パリ・オリンピックの開会式がセーヌ川で行われ、競技ではライバル関係にある複数国が一つの船に乗り込んだ様子を「呉越同舟」という故事に例えたものです。
四字熟語とは?
昔から言い伝えられたことわざや故事成語のなかでも、とくに四つの漢字を使って表した覚えやすいものを「四字熟語」といいます。もちろん二字、三字、五字のものもありますが、たった3つ、4つの漢字で、深い意味内容を表しているために、人々からよく使われるようになりました。
そのほとんどは中国の古典からきたものです。というのは、日本はもともと文字を持たなかったために中国から文字を仕入れ、当時の先進の文化を取り入れて日本語にしてきたからです。少し前までは「漢文」といって、日本でも中国の古典を学校で勉強していましたし、大学入試にも出題されてきました。ちょうど欧米の人がギリシャ語やラテン語の古典を勉強するのに似ていますね。
四字熟語は、人間の本質をついた鋭い警句であることが多く、現代においてもよく使われています。その言葉を知っているかいないかで、文章はもちろん、相手の話の理解度が大きく違ってくるほか、ぴったりとした場面で使うと自分の言葉が相手に与える印象が非常に強くなる効果があります。
現代の日本では、若い人を中心にだんだんカタカナ語の使用が増えてきて、四字熟語の意味や歴史までは知らない人もいます。それでも人間存在の真理をついたこのような漢字の言葉は、日本語の基礎として、またその人の教養を示すものとして非常に重要なものです。ここではよく使われる代表的なものを取り上げて、その意味や使い方などを紹介しましょう。
四面楚歌(しめん・そか)
さいきん、どこかアジアのある国の首相の評判が非常に悪く、支持率もぐんぐん下がっているために、自分の所属政党の内部からも批判がたくさん出ているといいます。新聞にも「批判続出で、首相は四面楚歌の状況だ」などと書かれています。
これは、もともと有名な中国の『史記・項羽本紀』の中のエピソードで、劉邦ひきいる漢の軍に追い詰められた項羽は、周囲の漢の軍の中から自分の出身地である楚の歌が聞こえてくるのを聞いて、もはや楚の地はすべて敵の手に落ち、周りに味方は一人もいなくなったのだと落胆するという話から来ています。四面(=周囲)はみな敵や反対者ばかりで、味方は一人もいない状況をさしていう言葉で、政治など、人間の対立を描く状況の中でよく使われています。
例
・教室には自分の意見に賛成する人はおらず、まったく四面楚歌となった。
・彼はたとえ四面楚歌となっても、がんばるつもりでいる。
羊頭狗肉(ようとう・くにく)
肉屋で、羊の頭を看板に掲げていながら、実際には狗(=犬)の肉を売ること。看板にはいい物をだして客を集めておいて、実際には粗悪な物をうること、つまり見せかけだけで、実質と一致していないことをいいます。中国古代の書『晏子春秋』や禅宗の書『無門関』などにある言葉。いつの時代のどこの国にもある見かけ倒しのいい例として、引用されることの多い言葉です。
例
・あの政治家は羊頭狗肉の公約ばかりで、何一つ実行していない。
・ネットには羊頭狗肉の詐欺広告が多いから気をつけないと……。
温故知新(おんこ・ちしん)
中国の古典である『論語』は春秋時代の思想家・孔子の言行をまとめたもので、日本でも昔から広く読まれた書ですが、これは、その「為政」篇にある孔子の言った言葉です。古い事柄に習熟した上で、新しいことも分かっている、そういう人であれば教師として尊敬できる、という意味です。古いことだけにこだわる人や、新しくて珍しいことのみを追いかけるようではいけないという戒めの言葉として、卒業式や入学式などの挨拶の中でよく使われます。
例
・昔から「温故知新」というように、人間は常に勉強することが必要なのです。
(この例のように、『論語』は広く読まれた書ですので、これ以外にも、いろいろと引用されることの多い古典です。)
朝三暮四(ちょうさん・ぼし)
昔、中国に猿回しの男がいました。ある時お金に困って、猿の餌を減らそうと思い、猿を集めて言いました。「これから餌の栃の実を朝3つ、夕方4つやろう」というと猿たちが怒ったので、「それなら朝4つ、夕方3つやろう」と言うと、猿たちは大いに喜んだという寓話からきたものです。中国古代の思想家・道家の人たちの本、『列子』や『荘子』などに見える故事で、どちらにしても大差ないことをごまかして言うことです。現代でも、「真摯に受け止めて」とか「全身全霊をもって」とか、たいしたことはしていないのに、ことごとしく言い立てる政治家がいたりします。これは有名な話ですが、国会で「朝ごはんは食べなかったのか?」と聞かれて「食べなかった」と答えた首相もいました(よく聞くと、首相は、パンは食べたのですが、ご飯(=米の飯)は食べていなかったそうです)。
例
首相の言うのは、「朝三暮四」と同じで、ごまかしではないですか!
(これと似た熟語に「朝令暮改」があります。これは朝に命令を出したと思えば、夕方にはそれを改め、むやみに法令を変更することをいいます。)
五十歩百歩(ごじゅっぽ・ひゃっぽ)
戦場において50歩逃げた兵士が100歩逃げた兵士を臆病だと笑うこと。わずかな違いはあるものの、戦わないで逃げたことでは同じなので、大きな違いがない、本質的には同じであることを言います。
孔子とならぶ中国古代の思想家の言行をまとめた本『孟子』の中にある寓話で、自分は善政を行っていると自負する王を隣国の王とあまり変わりないと諭す時に使われたものです。
2000年以上も前の中国の話が、現代の日本語の中に生きている典型的な例といえるでしょう。
例
・君の意見は小学生の意見と五十歩百歩だね。もう少しまともな意見はないのかね。
(などと、あまり変わりがないことを批判的に言うときに使います。)
次に二字の熟語の有名なものを紹介しましょう。これらは日常でも非常によく使われることばで、日本人の中にも、それらに故事(昔の言い伝え)があることを知らないで使っている人もいるかもしれません。
蛇足(だそく)
人間は、どうもよけいなことをしてしまう動物のようで、今から2000年以上むかしの中国の戦国時代の策略家たちの話をまとめた『戦国策』という本の「斉策上篇」にあるおもしろい話を紹介しましょう。昔、中国の楚という国で、お上からお酒が振る舞われたが、みんなで飲むには足らなかった。それで蛇を早く書き上げる競争をし、一番早くできたものがその酒を飲むことにしました。ある人物が一番先に蛇を描きましたが、彼は得意になって、どうだ早いだろう、俺は足を書く余裕もあるのだと蛇に足を描いてしまいました。すると足のあるのは蛇ではない、ということになり、2番目に書いた人が酒をもらった、という話です。それ以来、余計なこと、不要なもの、または余計な行為をすることを蛇足というようになりました。
例
君の発言は蛇足だよ(=よけいなことだ)。
(また、会議などで発言した後、「蛇足ながら……」と追加の話をするときにも使われます。)
矛盾(むじゅん)
中国の戦国時代の末期に韓という国があり、その王族に韓非(かんぴ)という思想家がいましたが、秦の始皇帝に毒殺されてしまいます。この「矛盾」という言葉は、彼の著書『韓非子(かんぴし)』「難一篇」の中にある逸話からできたものです。
昔、楚の国で武器を売っている商人がいました。その男は「この矛(ほこ)は、どんな盾(たて)でも突き通す素晴らしい矛だ」といい、一方で「この盾は、どんな矛でも防げる素晴らしい盾だ」と宣伝しました。それを聞いていたお客が「それなら、その矛で、その盾を突いたらどうなるのかね?」と聞くと、男は答えられなかったという話です。二つの主張の辻褄(つじつま)があわない、論理的に合わないことを言うときに使います。
例
君は、言っていることとやっていることが、矛盾している。
このほか、以心伝心、苦肉之策、画竜点睛、是是非非、疑心暗鬼、孟母三遷、完璧、指南など、日本語の中でよく使われている二字、三字、四字の熟語はたくさんあって紹介しきれないほどです。学校では、さまざまな種類の教科書を使って日本語を学びますが、このような中国の古典から日本語になった言葉も勉強します。みなさんも、TCJで豊かな日本語の世界に触れてください。
参考文献
松村明編『大辞林』三省堂書店
鎌田正・米山寅太郎著『漢文名言辞典』大修館書店