
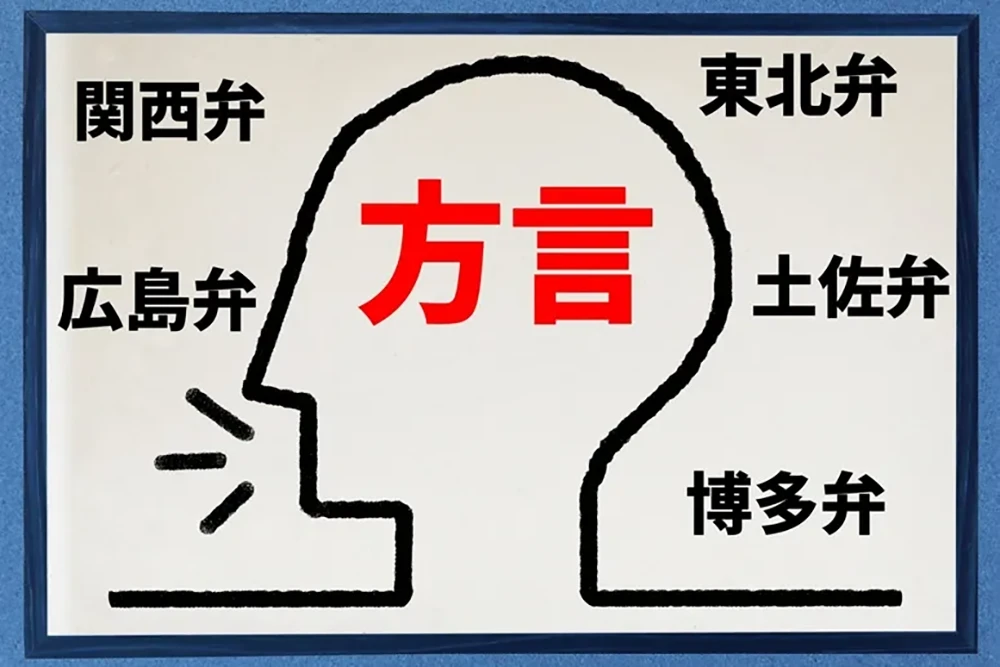
関西弁に標準語、関東弁に津軽弁?日本の方言をご紹介
みなさんは日本の方言を知っていますか。東京の言葉を基本とした標準語、大阪などで話されている関西弁は知っている人が多いと思いますが、実は、日本には40~50種類の主要な方言が存在すると言われています。「え!そんなに?」と思いましたか?
それでは、どんな方言があるのかをご紹介しましょう。
日本の方言
日本にはたくさんの方言があります。方言とは、ある特定の地域で使われる、標準語とは異なる言葉のことです。いくつかのグループに分けられ(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄など)、イントネーション(音の高低)、発音、単語、文法などが、地域によってそれぞれ独自の変化を遂げてきました。
日本は山や海で隔てられた地域が多く、昔は人々の移動も今ほど活発ではありませんでした。そのため、地域ごとにコミュニケーションの範囲が限られ、それぞれの土地で独自の言葉が発達していったと考えられています。
テレビやラジオ、インターネットなどの普及により、標準語が広く使われるようになり、特に若い世代を中心に方言の使用頻度が低下している地域もあるようです。方言は地域の文化や歴史を伝える大切な要素であるため、その継承が課題となっています。
その一方で、近年では方言の魅力が見直され、地域おこしや観光PRに活用されたり、方言をテーマにしたエンターテイメント作品が人気を集めたりする動きもあります。方言を学ぶと、その地域の人とより親密なコミュニケーションを取ることができたり、言葉を通して、その土地の歴史や考え方やユーモアのセンスなどを知ることができます。また、日本語の奥深さや、地域ごとの豊かな表現に触れることができます。機会があれば、ぜひいろいろな地域の方言に触れてみてください。
標準語(関東弁)
日本では、いろいろな場所で方言が話されていますが、みんなが違う言葉を使うと、意味が伝わらないこともありますね。そこでできたのが「標準語」です。標準語は、日本全国どこでもみんなが同じように話せる言葉で、みなさんが日本語を勉強するときに習う言葉です。
明治時代(1868~1912年)、日本の近代化を進める上で全国的に統一された言語が必要とされ、標準語が制定されました。東京が日本の中心地であったため、東京で話されていた言葉(東京語)が標準語の基盤となりました。そして、学校教育や公共の場などで標準語の使用が推奨され、テレビやラジオなどのメディアを通じて全国的に普及していきました。しかし、地域によっては独自の方言が根強く残っており、標準語と方言を使い分けている人も多くいます。
ここで、標準語に関するいくつかの誤解をあげておきます。標準語は、東京の言葉そのものではありません。また、常に変化しており、時代とともに新しい言葉や表現が取り入れられています。
それから、標準語は唯一の正しい日本語というわけではありません。方言もまた、日本の豊かな文化を構成する重要な要素です。
関西弁
関西弁は、大阪府、京都府、兵庫県を中心とした近畿地方で話されている日本語の方言の総称です。関西地方は、京都を中心に古くから日本の政治・文化の中心地として栄えてきました。そのため、関西弁は古い言葉や表現を多く残しており、豊かな歴史を持っています。江戸時代には、大阪が商業の中心地として発展し、独特の言葉遣いや表現が生まれました。これらの言葉は、現在も関西弁の特徴として残っています。
関西弁は、標準語と比べてイントネーションの上がり下がりが大きく、抑揚が強いのが特徴です。特に、文末の語尾が上がる傾向があります。
関西弁には、標準語にはない独特の語彙や表現が数多く存在します。例えば、「めっちゃ」(とても)、「ほんま」(本当に)、「あかん」(だめ)などがあります。関西弁は、親しみやすく、ユーモアに富んだ表現が多いのが特徴です。そのため、関西の人々は、日常会話で積極的に関西弁を使い、コミュニケーションを楽しんでいます。
また大阪弁、京都弁、神戸弁など関西地方内でもそれぞれ方言があり、独自の特徴を持っています。京都弁は上品で丁寧な言葉遣いが特徴であり、大阪弁は勢いがあり、ユーモアに富んだ言葉遣いが特徴です。関西弁は、その独特のイントネーションや語彙、表現によって、人々に親しみやすさや温かさを与えます。
ここで、よく耳にする関西弁を紹介します。
なんでやねん!
ツッコミの言葉としてよく使われます。ツッコミとは、主に漫才やコントなどの日本のコメディにおいて、ボケ(面白いことを言う人や、わざと的外れなことをする人)の発言や行動に対して、矛盾点や不自然な点、おかしな点などを指摘し、笑いを誘う役割のことです。
おおきに
感謝の言葉(「ありがとう」の意味)として使われます。
ちゃうちゃう
否定の言葉として使われます。
~へん
否定の助動詞として使われます。
~やん
断定の助動詞として使われます。
津軽弁、博多弁、広島弁、・・・いろいろな方言
日本には、関東弁、関西弁以外にも地域ごとに豊かな特色を持ついろいろな方言が存在します。ここでは、代表的な方言をいくつか紹介します。
津軽弁
津軽弁は、青森県の津軽地方(青森市より西の地域)で話されている方言です。標準語とはかなり違うため、「まるで外国語みたいだ」と感じる人もいるほど、独特な響きと表現を持っています。
特徴は、次のような点です。まず、言葉や文が短く省略される傾向があります。
「どこへ行くの?」が「どさ?」、「温泉に行くところです」が「ゆさ」のように短くなります。
それから、「が」「ぎ」「ぐ」「げ」「ご」「だ」「ぢ」「づ」「で」「ど」「ば」「び」「ぶ」「べ」「ぼ」といった濁音が多く使われます。
また、標準語とは音の高低のパターンが異なります。同じ言葉でも、意味によってイントネーションが変わることもあります。
「す」と「し」、「つ」と「ち」などの区別がなく、例えば、「寿司(すし)」も「獅子(しし)」も同じように「すし」に近い音で発音されます。
語尾も「〜だ」「〜です」などが「〜だべ」「〜すべ」のように変化します。また、疑問を表す時に語尾が上がったりします。
津軽弁をいくつか紹介します。
め(ぇ)・・・おいしい
け・・・食べて、ちょうだい、かゆい、毛 など、イントネーションで意味が変わります。
わ・・・ 私
な / おめ・・・あなた (初対面の人に使うと失礼になる場合があります)
へば・・・それでは、じゃあ
まいね:・・・だめだ
わいは! / どんだば!・・・うわー! / どうしたの!
かちゃくちゃねぇ・・・散らかっている、イライラする
めんこい / めごい・・・かわいい
じょっぱり・・・意地っ張り
博多弁
博多弁は、福岡県福岡市を中心とした地域で話されています。
博多弁は、語尾の「〜と」や「〜たい」などが優しく、親しみやすい印象を与えます。語尾のイントネーションが特徴的な、温かい響きの方言です。
特徴は、次のような点です。
標準語の「〜だ」「〜です」に相当する表現として、「〜たい」「〜やけん」「〜ばい」などが使われます。標準語の「〜たい」は「〜したか」、「〜ている」は「〜とる」、「〜から」は「〜やけん」「〜けん」が使われます。軽い断定・念押しで、「〜と」がよく使われます。「〜だよ」「〜だよ」といったニュアンスです。
博多弁を代表する語彙を紹介します。
好いとう(すいとう)・・・好きだよ
なんしようと?・・・何をしているの?
よか・・・良い
わるか・・・悪い
なおす・・・しまう、片付ける
つ・・・強い
むつかしい・・・難しい
ちかっぱ / ばり・・・とても、すごく
とっとっと?・・・取っておいてある?(相手に何かを尋ねる際の軽い挨拶としても使われることがあります)
〜ったい・・・(語尾につけて)〜だよ(ややくだけた言い方)
広島弁
広島県で話される広島弁は、力強く、少し語気が荒く聞こえることもありますが、親しみやすい温かい響きを持つ方言です。「〜じゃ」という語尾は印象的で、広島らしさを強く感じさせます。
全体的に平坦なイントネーションで、標準語のような音の高低の差が比較的少なく、単調に聞こえることがあります。
広島弁の最も特徴的な語尾は「~じゃ」で、「〜だ」「〜である」という意味を表します。「〜けえ」は「〜だから」という意味で使われ、「〜じゃけん」と強調する言い方もあります。「〜とる」は「〜ている」という意味で、動作の進行や状態の継続を表します。「〜ん?」「〜んか?」は文末につけて疑問を表します。「〜の?」「〜なのか?」という意味です。「〜とるん?」のように使われます。「〜しんさい」は「〜してください」という意味です。
有名な広島弁を紹介します。
ぶち・・・とても、すごく
えらい・・・しんどい、疲れた、大変だ
わや・・・めちゃくちゃ、ひどい
そがい・・・そうだね
よーけ・・・たくさん、多く
TCJでもっと日本語を学ぼう
代表的な方言を紹介してきましたが、いかがでしたか。魅力的な方言はまだまだあるので、調べてみてください。
TCJの先生たちは、日本語を教えるときは標準語ですが、出身はみんな違います。実は私も東京出身ではなく、茨城県出身です。TCJでいろいろな先生から出身地の方言を教えてもらうのも楽しいかもしれませんね。
ぜひ、一緒に日本語を学びましょう。









